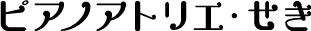こんにちは!
千葉市若葉区の当ピアノ教室HPをご覧いただき、ありがとうございます。
楽器の習得には自宅練習が欠かせません。
保護者のみなさんは、お子さんが自ら練習するのを望んでおられると思います。
今日は、私から保護者のみなさんへお願いしたいことをお伝えします。
Yちゃん(小1)のケース
Yちゃんのお母さまは、以前習っていた先生に「お子さんの練習をみてあげてくださいね」と言われたそうです。
私はお母さまが練習に関与しておられるのを感じて「Yちゃんはお母さんに何の音かききますか?」とお聞きしました。
「はい…」
「ひとりで楽譜を読めるように指導しますから、今後はきかれても答えを与えず【自分で考えて】とおっしゃってください」

後日お母さまよりメッセージをいただきました。
「実はYは私に分からないことをきいてきたことなど、一度もありませんでした。
なぜならYがきく前に私が全て教えていたからです。
ヘ音記号の音は読めません。
♯も♭も知らず、リズムも理解していません。
先生の所に来て【出された課題は1週間でしっかりできるようにしなきゃ】と私が勝手に思い込み、
練習中最初から最後までずっと横にいて一所懸命教えていました…
つまりひとりで練習したことがありません。
これからはあれこれ教えず、見守るというか、応援していこうと思うのですが、そういった認識でよろしいでしょうか?」

以下、私の返信です。
「私はYちゃんが体験レッスンの時に読譜を習っていないとお聞きしていましたので、読めない状態を想定していました。
その割に弾けているので、お母さまが教えておられると想像しました。
読譜できないのは、Yちゃんの問題です。
【弾けない娘を見るのは辛い】
【読めない子だと講師に思われたくない】
【親がしっかり見てやらないからだと思われたくない】
そのお気持ちから「自宅練習」をご自分の問題にしてしまうと
Yちゃんが自分の力でピアノ弾いて楽しむ将来が遠のいてしまいます。

困ったときが学ぶとき
「ママ~わかんない!おしえて!」
「それは〇〇よ」
いつも答えを与えてもらうと、どうなるでしょう…
答えにつながる道筋をさがすこと、つまり自分で考える力は養われません。
そしてレッスンで弾けないと「だって、ママが~と言ったから…」
弾けないのをお母さんのせいにしてしまいます。
「あら?習っているのはだれなのかしら?」
忘れたときに思い出すためのヒントや手がかりは、テキストやノートに書いてあります。
「あれ?なんだっけ?どうしよう」と考え、手がかりをさがせたら「そうだった!」と見つけられます。
お子さんが困る場面は、学ぶチャンスです。

練習させようとする声かけ
小学校低学年までのお子さんは、練習を習慣化するために保護者のみなさんに手助けしていただく必要があります。
そこでやってしまいがちなのが
「練習したの⁈」
返ってくる言葉は「今やろうと思ったのに…」
「お母さんの言い方が悪いからやる気がなくなった」
これを続けていても自ら練習するようにはなりません。

練習しやすくなる声かけ
「今日はピアノの練習を何時くらいにしようか考えているの?」
「5時くらい」
「そうなのね。考えているのね。よかった!」
ピアノを練習しようと考えていると確かめられると、落ち着いて見守れます。
そして5時になり、お子さんが取りかかれたら家事をしながら聴いてください。
間違いに気づいても弾いているだけで良しとしましょう。
「わかんない!おしえて」と言われたら
「あら、分からないのね。先生とやったことを思い出してみて」
「やっぱりわかんないもん!」
「考えても分からないのね。では分からないところにしるしを書いておいたら?先生に伝えられるよ」
これらの言葉は練習しやすい環境をつくります。
練習し終わったら「今日はあなたのピアノが聴けてよかった」と伝えましょう。
その言葉はお子さんが明日も練習しようする「やる気の芽」に陽の光・水・栄養を与えます。
では「5時よ」と声をかけても一向に始める気配のない場合にはどうしたらよいでしょう。
「練習すると言ったのに何故やらないの!?」これは禁句です。
「私が練習させなくちゃ!」という思いから離れましょう。
何か伝えるとしたら「今日はピアノが聴けなくて残念」
楽器習得には上達と共に「自立」という目標があります。
そうです!ピアノを練習できる子は自立へ歩む子です!

「うちの子、音楽が好きみたい」
「ピアノを楽しめたらいいな」とお考えのみなさま、ぜひレッスンを体験してご検討ください。
⇓体験レッスンのお申し込みはこちらよりお願いいたします。
無料体験レッスン